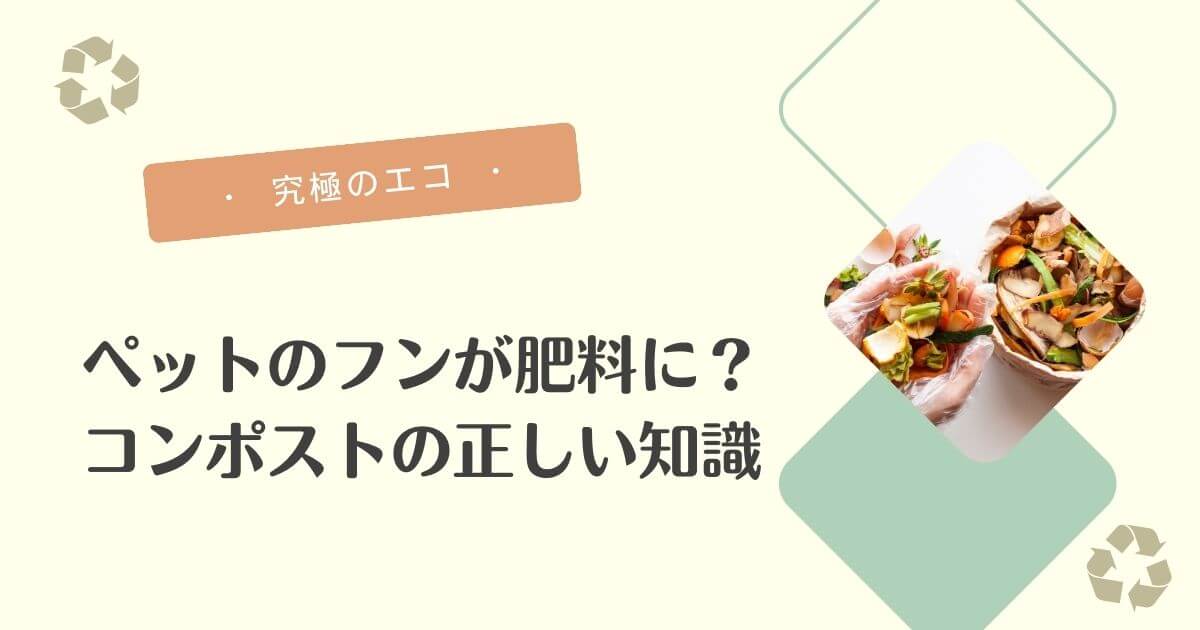「ペットのフンって堆肥にできるの?」
「家庭で処理する方法は? 臭いや衛生面は大丈夫?」
そんな疑問や悩みを抱えて、この記事にたどり着いたのではないでしょうか?
実際、ペットのフンをコンポストに活用することは可能ですが、正しい知識と方法が必要です。
なぜなら、ペットのフンには病原菌や寄生虫が含まれている可能性があり、間違った処理をすると悪臭や衛生問題の原因になるからです。
では、どうすれば安全にペットのフンを処理し、堆肥として活用できるのでしょうか?
この記事では、「ペットのフンを堆肥化する正しい方法」を詳しく解説します。
また記事後半では、楽にペットのフンを堆肥化したい人のための提案として、「生ごみ処理機」を使った処理方法も紹介します。
この記事を読めば、ペットのフンの適切な処理方法がわかり、毎日の負担が軽くなります。
手間を減らし、快適な環境を保つために、さっそく見ていきましょう。
\ ペットのフンを自動で堆肥化! /
ペットのフンをコンポストで処理するってどういうこと?

コンポストとは、生ごみや落ち葉、フンなどの有機物を微生物の働きで分解し、堆肥(たいひ)にする装置や方法のことです。
簡単に言うと、「自然の力を利用してゴミを栄養たっぷりの土に変える仕組み」です。
ペットのフンをコンポストにすることで、環境負荷を減らしながら有効活用できます。
ペットのフンを土にかえすしくみ
ペットのフンをコンポストで堆肥化するには、微生物の働きを利用して有機物を分解し、最終的に栄養豊富な土壌成分に変える必用があります。
- 微生物の活動
-
ペットのフンには有機物が豊富に含まれており、これをバクテリアやカビなどの微生物がエサとして利用します。微生物はフンの中の炭素化合物や窒素化合物を分解し、エネルギーを得ます。
- 温度の上昇
-
微生物の分解活動により、熱が発生します。コンポスト内の温度は50~60℃程度に上昇し、この高温環境がさらに微生物の活動を活発にします。また、高温により病原菌の死滅や臭いの軽減も期待できます。
- 水分と通気の管理
-
微生物の活動には適切な水分と酸素が必要です。フンに含まれる水分は微生物の活動を支えますが、過剰な水分は嫌気的環境を作り出し、悪臭の原因となるため、適度な通気性を保つことが重要です。例えば、落ち葉やおがくずを混ぜることで通気性を向上させ、微生物の活動を促進します。
- 最終産物の生成
-
微生物の分解活動の結果、フンは無機成分や安定した有機物に変わります。これらは堆肥として土壌改良材や肥料として利用でき、植物の成長を助けます。
微生物は、ペットのフンに含まれる有機物を栄養源として分解し、最終的には土に戻します。
まず微生物は堆肥の原料となる有機物に含まれる糖やアミノ酸を分解していきます。
ペットのフンを堆肥化する簡単な方法
ペットのフンを堆肥化するには、簡単な方法として段ボールコンポストを活用するのがおすすめです。
段ボールを使ったコンポストはコストが低く、自宅で手軽に実践できます。
段ボールコンポストを活用することで、ペットのフンを堆肥として再利用できます。
段ボールコンポストの基礎知識
段ボールコンポストとは、段ボール箱を利用して生ごみを堆肥化する方法です。
段ボールの通気性を活かし、微生物の働きで生ごみを分解・発酵させ、最終的に堆肥として再利用します。
特別な機材や電力を必要とせず、家庭で簡単に始められるエコな取り組みとして注目されています。
段ボールコンポストに必要なもの
段ボールコンポストを始めるには、いくつかの材料と道具が必要です。
| 項目 | 内容・用途 |
|---|---|
| 段ボール箱 | 防水加工されていないもの(40cm×35cm×30cm程度) |
| 中敷き用段ボール | 箱の底を補強し、強度を増すために使用 |
| ピートモス | 15リットル、生ごみの分解を促し、水分調整をする |
| くん炭(もみ殻くん炭) | 10リットル、臭いを抑え、微生物の働きを助ける |
| ガムテープ | 段ボールの補強や隙間を塞ぐために使用 |
| 新聞紙 | 底に敷き、余分な水分を吸収 |
| 覆い布 | 虫の侵入を防ぐ(古布・タオル・防虫ネットなど) |
| 設置台 | 段ボール箱を地面から浮かせる(ブロック・発泡スチロールなど) |
| スコップ | 生ごみと基材を混ぜる際に使用 |
段ボールコンポストの作り方(手順)
段ボールコンポストは、以下の手順で作ることができます。
- 側面と底がしっかりしている段ボール箱を選ぶ
- 内側に新聞紙を敷いて、湿気対策をする
- 通気性を確保するため、側面に数カ所穴をあける
- 段ボールの底に基材(ピートモス・もみ殻くん炭・腐葉土)を10cmほどの厚さで敷く
- これがペットのフンを分解する微生物の住処になる
- ペットのフンをそのまま入れず、乾燥させるか、刻んで入れる
- 1回に入れる量は少量ずつ(一気に入れると分解が追いつかない)
- 猫砂やビニールは絶対に入れない!(分解しないものはNG)
- 水分が多すぎると悪臭やカビの原因になる
- もし湿っている場合は、新聞紙や段ボール片を追加し、水分を吸収させる
- 1日1回、スコップで全体を混ぜる(酸素を入れるため)
- 表面だけ混ぜず、底の方までしっかり攪拌するのがポイント
- 乾燥しすぎているときは、霧吹きで少し水を足す
発酵が順調に進めば、1〜3カ月程度で堆肥として使用できるようになります。
完全に分解されていれば庭や植物の肥料として再利用可能です。
よくある失敗と対策
段ボールコンポストを使う際には、いくつかの失敗例があります。
| 失敗 | 原因 | 対策 |
|---|---|---|
| 悪臭がする | 水分が多い / 酸素不足 / フンを入れすぎ | 新聞紙や段ボール片を足して水分を調整する。1日1回しっかり混ぜて空気を入れる。フンは少量ずつ投入する。 |
| 分解が進まない | 温度が低い / 微生物のエサ不足 / 基材が少ない | 日当たりの良い場所に置く(冬場は特に注意)。米ぬかやもみ殻を足して発酵を促進する。ピートモスや腐葉土を追加する。 |
| 虫が湧く | フンが露出している / 生ごみがそのまま / 甘いものが多い | フンの上に土をかぶせる。生ごみは細かく刻んで混ぜる。フタをしっかり閉める。 |
| カビが生える | 水分が多い / 通気性が悪い | 新聞紙を敷いたり追加する。週1回、箱の位置を変えて風を通す。カビが生えた部分をすぐに取り除く。 |
| コンポストが湿っぽい | 水分の多いごみが多い / 水を足しすぎた | 水分の多い生ごみは事前に乾燥させる。新聞紙や段ボール片を増やして吸収させる。 |
| コンポストが乾燥しすぎ | 水分不足 / 乾燥したものが多すぎる | 霧吹きで少し水を足す(入れすぎ注意)。果物や野菜くずを混ぜる。 |
段ボールコンポストは、水分・空気・微生物のバランスが重要です。
悪臭や虫の発生は、水分が多すぎたり、通気が悪かったりすることが原因になりやすいです。
分解が進まない場合は、温度管理や発酵を促す基材を見直すと効果的です。
毎日適切に混ぜて、ごみの入れ方を工夫することで、スムーズな分解が進みますよ。
ペットのフンをコンポストにするときの注意点
ペットのフンをコンポストにする際には、いくつかの注意点を押さえる必要があります。
特に病原菌のリスクや臭い対策をしっかりと行いましょう。
安全な処理方法を知っておけば、安心してコンポストを活用できます。
病原菌のリスクと安全な処理方法
ペットのフンには、トキソプラズマ症や寄生虫などの病原体が含まれている可能性があります。
これらの病原体は、適切な処理を行わないと堆肥を介して人間や他の動物に感染するリスクがあります。
- 高温堆肥化
-
病原菌を効果的に死滅させるためには、堆肥の温度を55℃以上に維持することが推奨されています。具体的には、堆肥の中心温度を55℃以上で3日間以上保つことで、病原体の多くを効果的に減少させることができます。
- 適切な素材の選択
-
堆肥化する際には、肉類や乳製品などの腐敗しやすいものを避けることが重要です。これらの素材は強い臭いを発し、害虫や野生動物を引き寄せるだけでなく、病原菌の増殖を助長する可能性があります。代わりに、植物性の材料やおが屑、もみ殻などを使用しましょう。
これらの対策を実施することで、ペットのフンを安全に堆肥化し、病原菌のリスクを最小限に抑えることができます。
特に、高温堆肥化は病原体の死滅に効果的であり、適切な素材の選択は堆肥の品質向上と安全性の確保に影響します。
大腸菌やサルモネラ菌をはじめ、病原菌を死滅させるには、だいたい50~60度を1時間も保持すればいいと分かっています。
引用元:マイナビ農業
抗生物質を投与しているペットのフンは使える?
以下に 抗生物質を投与しているペットのフンの使用可否 についてまとめました。
| 項目 | リスク | 対策 |
|---|---|---|
| 微生物への影響 | 抗生物質がフンに残留すると、堆肥化を助ける微生物の活動を阻害し、分解が遅れる。 | 抗生物質を投与中および投与終了後1週間はフンをコンポストに入れない。 |
| 耐性菌のリスク | 抗生物質が堆肥中に残留すると、耐性菌が発生・拡散する可能性がある。 | 高温堆肥化(55℃以上)を行い、耐性菌のリスクを低減する。 |
| コンポストの品質低下 | 微生物が減少することで、発酵が進まず、悪臭や虫の発生リスクが高まる。 | 微生物を活性化させるために、米ぬかやもみ殻を追加する。 |
ペットのフンに抗生物質が残ると、微生物の働きが弱まり、堆肥化が進みにくくなります。
また、耐性菌の発生リスクもあるため、投与中および終了後1週間はコンポストに入れないことが推奨されます。
高温堆肥化(55℃以上)を行い、米ぬかやもみ殻を追加すると、分解がスムーズになりますよ。
近隣トラブルを防ぐための臭い対策
コンポストの臭いは、水分過多・通気不足・分解不良 が原因で発生します。
適切な管理をすれば、臭いを抑えて快適に堆肥化ができます。
- 1.水分管理
-
- 原因:コンポスト内の水分が多すぎると、嫌気性発酵が進み、悪臭の原因となります。
- 対策:生ごみの水分を減らすために、投入前に水気を切る。また、コンポストが湿りすぎている場合は、乾いた落ち葉や新聞紙、段ボール片を追加して水分を吸収させます
- 2.通気性の確保
-
- 原因:酸素が不足すると、微生物の活動が低下し、分解が不十分になり、臭いの原因となります。
- 対策:1日1回、スコップや棒でコンポスト全体をよくかき混ぜて、空気を取り入れます。これにより、好気性微生物の活動が活発になり、臭いの発生を防ぎます。
- 3.適切な素材の選択
-
- 原因:肉類や魚類、乳製品、油脂類などの腐敗しやすいものを投入すると、強い臭いを発生させます。
- 対策:これらの食品廃棄物はコンポストに入れないようにし、野菜くずや果物の皮などの植物性の生ごみを中心に投入します。
- 4.温度管理
-
- 原因:温度が低すぎると微生物の活動が鈍り、分解が進まず、臭いの原因となります。
- 対策:コンポストの温度を適切に保つために、日当たりの良い場所に設置し、必要に応じて保温材を使用します。また、発酵促進剤を使用して微生物の活動を活発にすることも効果的です。
- 5.害虫対策
-
- 原因:臭いに引き寄せられて虫が発生することがあります。
- 対策:生ごみは細かく切ってから投入し、投入後は土や基材でしっかり覆い、臭いを外に漏らさないようにします。また、コンポストの蓋をしっかり閉め、虫の侵入を防ぎます。
これらの対策を実践することで、コンポストの臭いを効果的に抑え、近隣トラブルを防ぐことができます。
もっと楽に堆肥化!生ごみ処理機という選択
ペットのフンを手間なく処理する方法として、生ごみ処理機を活用する方法もあります。
電動の処理機を使えば、臭いを抑えつつ、簡単に堆肥化できます。
生ごみ処理機を使えば、忙しい方でも手軽に堆肥化ができます。
生ごみ処理機の基本的な仕組み
生ごみ処理機は、加熱や微生物の力を利用して、フンや生ごみを分解・乾燥させる家電です。
| 処理方式 | 仕組み | メリット | デメリット | 適している人 |
|---|---|---|---|---|
| 乾燥式 | 温風やヒーターで生ゴミの水分を飛ばし、乾燥させる | ・ゴミの量が約1/5~1/10に減る ・臭いを大幅に軽減できる ・軽量で捨てやすい | ・電気代がかかる(1回約10円~30円) ・水分の多い生ゴミは処理しにくい ・完全な分解はしない | ・ゴミの量を減らしたい人 ・臭いを抑えたい人 ・手軽に処理したい人 |
| バイオ式 | 微生物(バクテリア)の力で生ゴミを分解・消滅させる | ・生ゴミをほぼゼロにできる ・堆肥として再利用可能 ・電気代がかからない(撹拌用モーターを使う機種もあり) | ・こまめな管理(バクテリアの活性化)が必要 ・肉・魚など一部処理しにくいゴミがある ・設置場所を選ぶ(屋外向けが多い) | ・堆肥を活用したい人 ・環境に配慮したい人 ・ランニングコストを抑えたい人 |
| ハイブリッド式 | 乾燥+バイオの2つの方式を組み合わせ、生ゴミを分解・減量 | ・生ゴミをしっかり分解&減量できる ・臭いがほとんど出ない ・手間が少なく、管理が簡単 | ・価格が高め(高機能なため) ・定期的なバイオ材の交換が必要 | ・手軽に生ゴミ処理したい人 ・臭いを抑えつつ、しっかり分解したい人 ・維持費がかかっても手間をかけたくない人 |
引用元:テラル株式会社
バイオ式は自然な分解を促し、乾燥式は素早く処理できるのが特徴です。
それぞれの方式にメリットがあるので、ライフスタイルに合ったものを選びましょう。
導入のメリットと注意点
生ごみ処理機を導入すると、ペットのフンを効率的に処理できるだけでなく、環境にも優しいメリットがあります。
しかし、導入にはコストや設置場所などの注意点もあるため、事前に確認しておきましょう。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 生ごみの量を減らし、ゴミ出しの回数を減らせる。 悪臭や虫の発生を防ぎ、衛生的。 堆肥として再利用でき、環境に優しい。 家庭で手軽に処理できるため、便利。 | 初期費用やランニングコストがかかる。 設置スペースが必要。 機種によっては処理できない生ごみがある。 定期的なメンテナンスが必要。 |
電動の生ごみ処理機は、手間をかけずにペットのフンを処理できるため、忙しい方におすすめです。
ただし、定期的なメンテナンスや運転コストについても考慮する必要があります。
次に、生ごみ処理機を使用する際のポイントを紹介します。
コンポストとの違い
| 項目 | コンポスト | 生ゴミ処理機 |
|---|---|---|
| 処理方法 | 微生物の力で分解 | 電気で乾燥・分解・脱臭 |
| 処理時間 | 数週間~数ヶ月 | 数時間~1日 |
| 臭い対策 | 管理を怠ると臭いが発生 | 脱臭機能があり臭いを抑えられる |
| 維持費 | ほぼゼロ | 電気代や消耗品のコストがかかる |
| 設置場所 | 屋外(庭・ベランダなど) | 室内(キッチンなど) |
| 処理後の活用 | 堆肥として再利用できる | 基本的に廃棄するが、一部機種は堆肥化可能 |
コンポストは 微生物の力で自然分解 し、堆肥として再利用 できるのが特徴です。
一方、生ごみ処理機は 電気を使って素早く乾燥・分解 し、臭いを抑えつつ処理 できる利便性があります。
設置場所や維持費も異なるため、使用環境や目的に応じて選ぶことが重要 です。
ペットのフン処理ができる生ごみ処理機は2つ
| 生ごみ処理機 | 公式サイト | 型番 | 主な用途 | 価格 | 維持費 | 電気代目安 | 処理方式 | 主な機能 | 脱臭機能 | 運転音量 | サイズ | 重量 | 消費電力 | 処理能力 | 処理時間 | 保証 | メーカー | 推奨ユーザー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ワンニャクスル | 公式サイトはこちら | FD-020 | ペットのフン処理に特化(生ごみも処理可能) | 220,000円(クーポン適応で132,000円) | UVランプ(1~2年に1回):16,500円/本 バイオ材:8,800円(適切に使用すれば定期交換不要) | 1日あたり約28円 | ハイブリッド式 | 全自動処理・水分量センター・自動節電モード・脱臭機能・除湿機能 | ハイブリッド脱臭システム(悪臭成分を99.84%除去) | 30db以下(17.3db~23.2db) | 幅39×奥行43×高さ59.4cm | 約18kg(バイオ材含む) | 約60W | 最大投入量/1日:2.0kg | ペットのフン:約12時間 生ごみ:約24時間 | 1年間の無償修理保証 | 株式会社伝然 | ペットのフン処理を日常的に行う人 |
ナクスル | 公式サイトはこちら | FD-015M | 生ごみ処理がメイン(ペットのフンも処理可能) | 139,700円(クーポン適応で99,000円) | UVランプ(1~2年に1回):16,500円/本 バイオ材:8,800円(適切に使用すれば定期交換不要) | 1日あたり約28円 | ハイブリッド式 | 全自動処理・自動節電モード・脱臭機能・除湿機能 | ハイブリッド脱臭システム(悪臭成分を99.84%除去) | 30db以下(17.3db~23.2db) | 幅38.5×奥行43×高さ58cm | 約18kg(バイオ材含む) | 約60W | 最大投入量/1日:1.0~1.5kg | 約24時間 | 1年間の無償修理保証 | 株式会社伝然 | 生ごみ処理がメインで、ペットのフンを処理できる機能も欲しい人 |
2025年2月現在、ペットのフンを処理できる生ごみ処理機は2つです。
それぞれのスペックを比較します。
1日最大2kg!大量のペットのフンを処理したいならワンニャクスル
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 製品名 | 家庭用生ごみ処理機ワンニャクスル(OneNya NAXLU) |
| 型番 | FD-020 |
| 主な用途 | ペットのフン処理に特化(生ごみも処理可能) |
| 価格 | 220,000円 クーポン適応で132,000円 |
| 維持費 | <UVランプ> (1~2年に1回) 16,500円、1本 <バイオ材> バイオ材は、適切に使用すれば定期的な交換は不要(使用不能時のみ) バイオ材: 8,800円 ※公式では1~2年で交換を推奨 |
| 電気代目安 | 1日あたり約28円 (1kWh単価20.0円で算出) |
| 処理方式 | ハイブリッド式 |
| 主な機能 | 全自動処理 水分量センターで水分量を可視化 自動節電モード搭載 脱臭機能 除湿機能 操作ディスプレイ |
| 脱臭機能 | ハイブリッド脱臭システム 悪臭成分を99.84%除去 |
| 運転音量 | 30db以下(17.3db~23.2db) |
| サイズ | 幅39×奥行43×高さ59.4cm |
| 重量 | 約18kg(バイオ材含む) |
| 消費電力 | 約60W |
| 処理能力 | 最大投入量/1日:2.0kg |
| 処理時間 | ペットのフン:約12時間 生ごみ:約24時間 |
| 保証 | 1年間の無償修理保証 |
| メーカー | 株式会社伝然 |
| 推奨ユーザー | ペットのフン処理を日常的に行う人 |
| 公式サイト | 公式サイトはこちら |
- ペットのフンを効率よく処理し、臭いや水分を抑える。
- 生ごみも処理できるため、キッチンのごみ問題も解決できる。
- 99.84%の強力な脱臭機能で、室内でも臭いが気にならない。
- 水分量センサー搭載で、フンの水分量を可視化し最適に処理できる。
- 全自動処理で、蓋を開けて捨てるだけで処理が開始される。
- 1日最大2.0kgの処理能力があり、フンや生ごみをまとめて処理できる。
- 低騒音設計(30dB以下)で、夜間でも音が気にならない。
- 操作ディスプレイ付きで、初心者でも簡単に使える。
ワンニャクスルは、ペットのフンの処理に特化した高性能な生ごみ処理機で、臭い対策や処理能力に優れています。
生ごみも同時に処理できるため、キッチンのごみ問題も解決できる点がメリットです。
初心者でも簡単に使える全自動設計と操作ディスプレイが搭載されており、手間なく清潔な環境を維持できます。
\ 75,000円オフ! /
こまめに追加投入OK!生ごみ処理がメインのナクスル
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 製品名 | 家庭用生ゴミ処理機ナクスル(NAXLU) |
| 型番 | FD-015M |
| 主な用途 | 生ごみ処理がメイン(ペットのフンも処理可能) |
| 価格 | 139,700円 クーポン適応で99,000円 |
| 維持費 | <UVランプ> (1~2年に1回) 16,500円、1本 <バイオ材> バイオ材は、適切に使用すれば定期的な交換は不要(使用不能時のみ) バイオ材: 8,800円 ※公式では1~2年で交換を推奨 |
| 電気代目安 | 1日あたり約28円 (1kWh単価20.0円で算出) |
| 処理方式 | ハイブリッド式 |
| 主な機能 | 全自動処理 自動節電モード搭載 脱臭機能 除湿機能 |
| 脱臭機能 | ハイブリッド脱臭システム 悪臭成分を99.84%除去 |
| 運転音量 | 30db以下(17.3db~23.2db) |
| サイズ | 幅38.5×奥行43×高さ58cm |
| 重量 | 約18kg(バイオ材含む) |
| 消費電力 | 約60W |
| 処理能力 | 最大投入量/1日:1.0~1.5kg |
| 処理時間 | 約24時間 |
| 保証 | 1年間の無償修理保証 |
| メーカー | 株式会社伝然 |
| 推奨ユーザー | 生ごみ処理がメインで、ペットのフンを処理できる機能も欲しい人 |
| 公式サイト | 公式サイトはこちら |
- 生ごみ処理がメインで、ペットのフンも処理可能。
- 99.84%の強力な脱臭機能で、臭いを抑えながら処理できる。
- 全自動処理で、蓋を開けて捨てるだけで簡単に使える。
- 自動節電モード搭載で、省エネ設計になっている。
- 1日最大1.0~1.5kgの処理能力で、家庭の生ごみを効率よく処理できる。
- 低騒音設計(30dB以下)で、夜間でも気にならない。
- 設置スペースは必要だが、一般的な家庭での使用に適している。
ナクスルは、生ごみ処理をメインに考えている人に向いており、ペットのフンも処理できる汎用性の高さが特徴です。
強力な脱臭機能や自動節電モードを搭載しており、使い勝手が良く、省エネ設計になっています。
価格も比較的抑えられており、初めての生ごみ処理機として導入しやすいモデルです。
\ 37,000円オフ! /
ペットのフンをコンポストで処理FAQ
- ペットのフンは堆肥にできるの?
-
はい、ペットのフンを堆肥にすることは可能ですが、適切な処理が必要です。ペットのフンには病原菌や寄生虫が含まれる可能性があり、適切な方法で管理しなければ悪臭や衛生上の問題が発生する恐れがあります。
- ペットのフンを堆肥化する方法は?
-
家庭で手軽にできる方法として「段ボールコンポスト」があります。段ボールにピートモスやくん炭を敷き、少量ずつフンを投入しながら攪拌し、適切な水分管理を行うことで分解が進みます。
- ペットのフンを堆肥にする際の注意点は?
-
ペットのフンには病原菌が含まれる可能性があるため、高温で堆肥化することが重要です。また、水分や通気の管理を適切に行わないと悪臭や虫の発生につながります。猫砂やビニールなど分解しないものは入れないようにしましょう。
- 生ごみ処理機を使ってペットのフンを処理できる?
-
はい、ペットのフンを処理できる生ごみ処理機もあります。特に「ワンニャクスル」や「ナクスル」などの機種は、臭いを抑えつつフンを分解・乾燥できるため、手間をかけずに処理したい方におすすめです。
ペットのフンを堆肥にできる?まとめ
- ペットのフンはコンポストで堆肥化できるが、適切な処理が必要
- 段ボールコンポストを使えば、家庭で簡単に堆肥化可能
- 臭いや病原菌のリスクを防ぐため、水分・通気・温度管理が重要
- 抗生物質を投与されたペットのフンは使用を避ける
- 手間を減らすなら、生ごみ処理機の活用もおすすめ
ペットのフンをコンポストで処理すれば、環境に優しく堆肥として再利用できます。
しかし、病原菌のリスクや臭い問題を防ぐためには、適切な管理が必要です。
特に水分・通気・温度のバランスを取ることが大切ですよ。
手軽に処理したい場合は、生ごみ処理機の導入も一つの選択肢です。
電動の処理機なら、臭いを抑えつつ、短時間でフンを分解できます。
用途に応じた方法を選び、快適な環境を整えましょう。